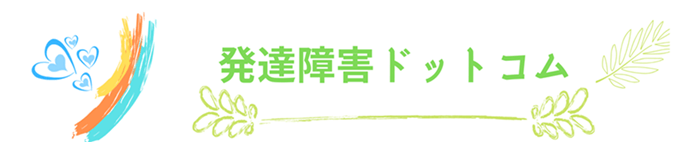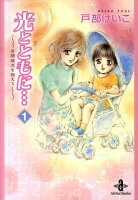『甘えたくても甘えられない: 母子関係のゆくえ、発達障碍のいま』小林隆児-発達障害の方におすすめな自己啓発・メンタルヘルス本-
ここでは、ADHDやASD、LDなどの発達障害だけでなく、精神障害・うつ病などの二次障害の方々にもおすすめな自己啓発本・メンタルヘルス本をご紹介していきます。
当事者の方々にアンケートを取り、その中でも特に人気が高かった本を掲載しております。
また、実際の当事者の方々の本紹介レビューもあわせてご覧ください!
『甘えたくても甘えられない: 母子関係のゆくえ、発達障碍のいま』小林隆児
本書では、心理学実験で使われる、「ストレンジ・シチュエーション・プロシジャー」という方法を使い、幼児と母親に協力してもらい、母親がいるときに見知らぬ人が同じ部屋に来ると、子供はどう反応するか、さらに母親が子供だけを残して出た行ったとき、どのような態度をとるか、さらに子供が見知らぬ人といたところに母親が戻ってくると、子供はどう母親に対して振る舞うかなどについて調べています。
多くの場合は、子供は母親に対して、様子をうかがいながら部屋を探索して遊びますが、見知らぬ人が入ってくると、母親の元に戻り、様子を伺います。
しかし、一部の子供は、見知らぬ人が入ってくると、明らかに不安そうなのに、母親に近づかず、不安を処理できずに常同行動などを始めます。
そして見知らぬ人と残されたのち、母親が帰ってきても、母親に甘えたりせず、不満そうに母親に対して距離を置いたまま行動します。
このような、言語以前の所で子供がどうのような情動をもっているかなどを、解りやすく解説してある本は少ないです。
子供がどう感じ、どう行動するかがあらかじめ解れば、こちらも動揺することも減り、余裕ができます。
大変役に立つ一冊です。
たまご・39歳・男性
本書では発達障害傾向の見られる子供の対人関係の取り方や行動について、母子に協力してもらいミラールームで観察しています。
発達障害の傾向のある子供が、いかに母親に関心を持ちながら、それを出さないようにしていて、母親がそばにいても、自分で何とか不安を処理しようとしているかが解りやすく解説されています。
日本語にしかない「甘え」という言葉を使うと、それが解りやすく描写できますので、深い知識のない人にも解りやすく解説できています。
認知科学や脳科学の本を読むより、こちらの研究の方が全体像が見えて役に立つ本だと思います。
自閉傾向のある子供がどのような思いでどのような行動をとるかがあらかじめ解っていれば、保護者や療育関係者も余裕ができて良いと思います。
あくまでも前言語的な所での行動についての研究なので、本書の図を使った解説を見ないと解らないと思います。
著者は1975年九州大学医学部卒、この著作のもととなる知見は、東海大学健康科学部社会福祉学科教授時代に行われた、ストレンジ・シチュエーション・プロシジャーをつかった研究に基づいた観察により得られたものに多くをよっています。
ゆでた・30代・男性