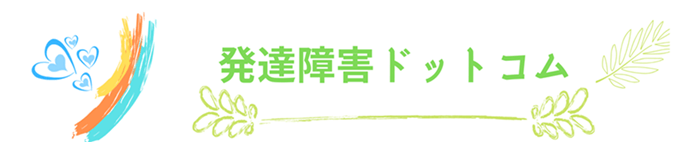Nさんから投稿頂きました。ありがとうございます。
私は幼少期に高機能自閉症(診断当初)と診断され、後にアスペルガー症候群と診断名が変更になった30代女性です。
小中学生時代は特別支援学級に在籍、高校と大学は私立の女子校、女子大を卒業しました。学生時代を通して感じたことが、発達障害を持つ方のために少しでも役立てればと思い、投稿します。
先述の通り、小中学校では支援学級に在籍していたものの、ほとんどの教科を通常学級で受けていました。しかし、小学校高学年から周りと馴染めなくなり、通常学級の担任の理解もあまりない中で過ごしました。小学校に於いては90名ほどの学年の中で支援学級在籍は私一人。同級生からすれば、障害のある子は奇異な存在にしかみえなかったのでしょう。あからさまに「お前、IQいくつだ?」と聞いてきた男子もいました。
本来であれば、教師が障害のある子のことを理解して接し方を生徒達に教えるはずだが、その教師自身が理解できないから教えられない。
だから、通常学級の担任からできる限り排除をされた年もありました。「面倒見切れない」と。提出物を出そうとするも、「それは支援学級で出してくれる?」と言われたこともあります。
考えてみればわかりやすい知的障害はともかく、発達障害はここ最近でようやく認知されつつある障害。
現役教師や親世代が子どもだったころはそういった障害の認知度が低かった。だから、障害を知らないまま大人になり、今初めて障害を知る。ましてや小学校教師を目指そうとする人はひと通り何でもできる優秀な人であろうから、できない子の気持ちがわからないのかもしれない。
特に発達障害はどこまでが特性でどこからがその子自身の性格なのかが曖昧で分かりづらい。
普通の世界しか知らない大人と障害のある子どもの温度差はどうしても埋まらない。
人は自分と違うものや人は理解できないのが性。聖人君子ではないのだから、どんな人間でも感情はあるし、全ての人に優しく接するなんて不可能なのだ。
私が小中学生だった1990年代後半~2000年代にかけてはまだまだ理解がなかった発達障害も、ここ最近で理解されつつある。しかし、ただ「理解してあげましょう」では障害のある子供達は成長できなくなってしまう。周囲が理解しようとする姿勢も大事だけど、障害のある子達だって周囲に受け入れられる努力をする必要がある。
私は周囲と上手くやれるように、失敗を重ねながらも対人関係を学んでいきました。一般的にはどういう行動が敬遠されるのか、逆にこういう行動が喜ばれるのかを周囲の人の動きや雑誌、ネットのコラム等でいつも研究していました。障害は個性ではない。障害は障害。普通や平均値を知ることだって大切。
「障害があるから仕方がない」という風に社会はできていないので、受け入れてもらえるように、悪いところは改善しながら成長しなくてはいけないと思うのです。
「理解して」「受け入れて」だけでは社会では通用しないことを皆さんにお伝えしたいのです。