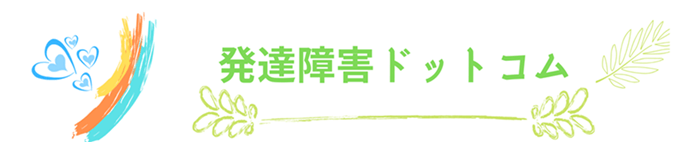【体験談】「息子がASD、かんしゃくに悩んだ日々」ーりこ・30代・女性
もくじ
①名前・年齢(年代)・性別
りこ・30代・女性
②発達障害の種類・診断名
ASD(自閉症スペクトラム障害)
③発達障害に気付いたきっかけ
現在小学1年生の息子が、自閉症スペクトラム症です。
言葉が遅く、1歳半を過ぎても一言も出なくて、2歳を過ぎても言葉が出なかったことが、発達障害を疑うきっかけでした。
それからはネットで検索して、発達障害の特徴を調べると息子がよくやっていた「ミニカーをひたすら並べる」や「さかさバイバイ」、偏食、かんしゃく、大人の真似をあまりしない、などがあり、おそらく発達障害なのだろうと思いながら過ごしていました。
診断を受けるには3歳を過ぎないとはっきりしたことは分からないとのことで、3歳を過ぎてから病院で診断を受けて、やはり発達障害だったか、という感じでした。
④発達障害で困った経験・悩み
困った経験や悩みはたくさんありますが、一番は、かんしゃくです。
自閉症スペクトラム症である息子は、気持ちの切り替えが苦手で、いったん嫌な気持ちになってしまうと、そこからなかなか気持ちを立て直せずにかんしゃくという形でしばらく大泣きしたり、母である私を叩いたり、物を投げたりして、暴れます。
6歳の今はタイムアウトを使っているので、そこまで長引くことは減ってきてはいますが、1歳〜5歳くらいまではそれが始まるとおさまるまでに1時間はかかり、かなり苦労しました。
家でのかんしゃくはまだいいのですが、外でのかんしゃくはかなりつらかったです。
例えば2歳の頃、「図書館へ行こう」と行って出かけたところ、定休日で開いてないことがあり、説明をしても納得できない息子はその場でかんしゃくを起こし、その激しさで何事だと人だかりができてしまったこともありました。
外でのかんしゃくは、ひたすら起こさないように気をつけてはいますが、予測できないかんしゃくが起きてしまうことも多々あり、苦労しました。
見た目は普通の子なので、「しつけのできてない子どもだ」とか「親が泣き止ませないのが悪い」とか「うるさい」と思われてるだろうなぁと感じました。
⑤発達障害の悩み・生活上の支障への対策や改善策
見た目には分からない障害なので、周りの人からの理解が得られにくい障害だと感じます。
よく周りのお母さん達と「障害あります!」って看板ぶらさげときたいよね〜なんて話もしていました。
今のところ母親である私が困っているのはかんしゃくですが、本人は人とのコミュニケーションが苦手なので、今後人間関係はしんどいだろうなと予測しています。
かんしゃくは、少しずつ減ってきていますし、幼い頃からとにかくとことん気持ちに寄り添ってきて、気持ちの共感をたくさんしてきたので、親子の信頼関係はできていると思います。
かんしゃくにはタイムアウトが効果的だと思いますが、時期やその子の発達段階に合わせて、専門家の意見を聞いてからやった方がいいと思います。
タイムアウト法もただ立たせるものや、部屋に閉じ込めて1人の時間を作ってクールダウンさせるものなど、いろいろあります。その子に合った方法が効果的だと思います。
今後は楽しいことや、しあわせなことをたくさん増やしてあげたら、手をあげることは少なくなるだろうと専門家の方から言われているので、そういった楽しいことを増やしていけるように家庭では取り組んでいこうと思っています。
とにかく家庭や親、本人だけの力ではいろいろと難しいので、市や、福祉の力を借りて周りの方に助けを求めていくことが大事だと思います。
⑥発達障害の方へのメッセージ
発達障害という言葉は、だんだんテレビなどでも取り上げられるようになり、知っている人が増えてきてはいますが、まだまだ中身についてはあまり詳しくない方がほとんどです。
いまだに偏見があったり、理解が得られにくかったりする状況だと思います。なので、発達障害の方はまだまだ暮らしづらい世の中だと思います。
しかし、発達障害の方はどんどん増えています。今後、もっと理解が進んでいくと信じています。
「障害があるから」という理由で、人生を諦めないでほしいです。