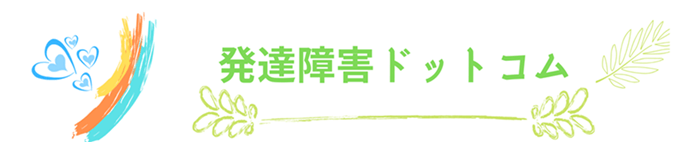【インタビュー】パレット稲毛海岸さん
千葉県千葉市、JR京葉線 稲毛海岸駅から徒歩3分のところにある障害者就労移行・定着支援事業所『パレット稲毛海岸』さんの取材に伺いました。
精神、知的、発達、身体障害、難病を抱える方へ、『パレット』の名前の通りお一人おひとりの色に合わせた就職支援を行われています。
そちらの施設長、生活支援員である宍倉 涼太さん、サービス管理責任者である三橋 幸太さんにお話を伺いました。
もくじ
職員もやりがいを感じ楽しむプログラム
――『パレット稲毛海岸』さんの就労プログラムについて、お聞きします。
まず目を引いたのは皆さんが同じ学習ではなく一人ひとり違うということですが、それはその人その人の個性に合わせてというのが強いのでしょうか?
宍倉さん 基本的に就労移行支援を使う方の目標というのは、最終的には就職だと思うんですけど、それまでの過程で生活リズムを整えることだったり資格を取得したり、人間関係やコミュニケーションに関して距離間を覚えていったりなど、越えなければいけない壁というか課題が皆さんバラバラで、
そういった人に合ったイベントや講座を出来るだけ提供したいと思っているので、
イベントであっても「この方に参加してもらいたいな」と考えながら計画をしていますね。

前職は教員をされていた宍倉さん
――ではイベントを始める時に個人にスポットを当ててということが多いのでしょうか?
宍倉さん 割とスポットを当てたりすることが多いですね。あと職員も楽しみたいところも結構強かったりしますけど(笑)仕事するにあたってやりがいを感じているのが一番大事だと自分は思うので、イベントや講座を主催する職員も一緒に楽しめるというのを大事にしたいと思っています。
三橋さん 私は前職で主に知的障害のある方が過ごす障害者施設で働いたのですが、そこでも季節行事や地域との交流などをよく行っており、そのときの経験を基に考えています。
パレットでは発達障害の方と精神障害の方が多く、前職の仕事とは異なりますが、ここではイベントについての会議で利用者さんが楽しみながら参加できる季節行事はないか考えるなど、まず利用者さんがイベントに参加するまでの敷居を低くしようと考えながら企画しています。
まず職員が楽しむというのも大切だと思いますが、生活リズムが整わずここに通所するだけでも結構大変な方々もいらっしゃるので、自分が同じ立場だったらどういったところに行きたいかというと楽しい所や面白い所やあるいは会ってみたい人や話したい人がいるところだと思うので、
利用者さんの心理的なハードルを出来るだけ低くして、今日も楽しんでもらって明日も楽しんで来てもらえるようなイベント作りというのを考えてますね。

サービス管理責任者の三橋さん
自立とはなにか
三橋さん 2月にパレットに入ったばかりなのですが、最近研修に出たり調べたりする中で「自立」という言葉をよく見掛けるんですね。元々自分がイメージしていた、自立というのは「なんでも一人でやることが自立なのかな」と思っていましたけど、「頼ること」と書かれていたりして、確かにそうだなと思いました。
専門機関だったり、今あるサービスをうまく使ってご自身で出来るようになることが自立なのだと思いました。
なので利用者さんと面談をする中で、利用者さんから「私自立出来てないんで」って言葉が出てきたり「自分の悪い所を履歴書などに書いたら採用してくれないのではないか」という方がいますけど、障害福祉サービスを上手に利活用できていないなと感じることがあります。
企業側は障害者雇用をして行く上で一人ひとりに合った働き方の実現を目指しているので、
自分の苦手なところを理解しある程度配慮してもらったりだとか、一緒に寄り添って仕事をしてもらうために障害の特性など正直に伝えてもっと頼ればいいと思います。
私にとっての『自立』の言葉の意味は「何かに頼ることで自分の人生を豊かにしていくこと」だと思っています。なんでも自分で一人で出来ることが自立ではないと思っています。

利用者さんが自ら描いた職員の方の似顔絵
――本質的な話になりますけども、お二人にとって発達障害のある利用者さんに対して、気を付けている取り組みや逆に背中を押すような働きかけはどういったことがありますか?
三橋さん 私自身、吃音があり「おはようございます」「ありがとうございます」など話しづらいワードがあったりして発達障害になるんですけれどね。
私が福祉の仕事に携わってきたのは妹が知的障害だったからというのもあるのですが、妹が生きていた頃に何もしてあげられず、亡くなったあとに「もう少し出来ることはあったんじゃないか」と思って障害者福祉の道に進んだというのがあります。
福祉の大学や専門学校に行って資格を取ったり勉強をしてきた人間ではないので、現場叩き上げという言葉が私にふさわしいかどうかは分からないのですが、自分の中で「こうあるべきだ」という言葉は頭の中に持っていないですね。
過去の辛かったことや生きづらさというのはパレットを利用している方は誰しも少なからず経験してきていると思うので、過去の経験してきた内容や今抱えている問題が障害ゆえのことなのか、本当は違うことなのかそこで私自身自分で判断しないで、悩みや不安は解決出来ないかもしれないんですけど「そうなんだね」と共感することから始めています。
普段は支援者側として上から目線にならないようにフラットな関係で、いつも笑ってもらえるくれる存在でいられたらいてもらえたらいいなと思っているので、冗談を言ったりふざけてばかりいるんですけど(笑)
だからいつも利用者さんと同じ立ち位置で話を聴くようには心がけていますね。
――「受け止める」というのが三橋さんからは感じられますね。
三橋さん 今ここを利用されている方は基本的には意思表示が出来たり、本来自分の考えを持っていてきちんとそれを相手に伝える術が元々備わっていたり身に付けることが出来る方たちであると思ってます。
就労移行を利用される方のゴールというのはまずは就職すること、定着することで突き詰めていえば人生を豊かにさせることというのがあるはずなのでそれに向かって伴走出来ればいいなと思っています。
宍倉さん 発達障害だけに限らないんですけど、その人の特性ってみんなバラバラなのでそこはちゃんと職員間で理解をしあって情報共有は徹底的にして、その人が「パレットに来て良かったな」と思ってもらえる事業所づくりをやっていきたいと思います。
自分たちの仕事って、その人たちに「やっぱり仕事って怖いものなんだ」「仕事って大変なものなんだ」って思われたらダメな仕事だと思うんです。やっぱりやることに責任感を持ったりだとか「仕事って生きていく上で必要なものなんだな」と思ってもらい、楽しいと思ってもらう。
もちろん仕事の中では楽しいと思えない仕事もたくさんありますけど、「やってて良かったな、楽しかったな、明日も頑張ろう」と思えるようになるのが重要になっていくと思うので、利用者さんからしてみれば働いてる人たちって私たちなので、
私たちが「仕事大変だな、辛いな」っていう姿は見せないことが、利用者さん全体に対しての配慮というか自分たちが出来る仕事の良さというのが見せられるのかなと思ってますね。
職員の方が楽しむことで利用者の方が「仕事って楽しいんだ」と思っていただけるようになる(こちらは来年のオリンピックのコスプレ)
様々なイベントで培われる自主性
――HPを拝見させていただいたのですが、パレット銚子の方と合同イベントを行った際に参加された利用者の方で「普段会わない人たちとコミュニケーションが取れて良かった」というコメントが多かったことが目を引きました。
こちらもコミュニケーションを意識して立てたイベントだったのでしょうか?
宍倉さん そうですね、事業所同士で連携を図りコミュニケーションを意識したイベントをやりたいというのは前々から話していて。
自分たちも初めての試みで利用者さんが来てくれるかどうか、うちの事業所の中でコミュニケーションは取れているけど初めて会う方とコミュニケーションを取るのって難しいじゃないですか。
ですがお互いの利用者さんが積極的に話しかけて、最後「またね」「また今度会いましょう」と言い合ってるのを見ると、「やってよかったな」と思えて、少なからずコミュニケーションという課題はクリアできたのかな、1人でもいれば「やって正解だったのかな」とは思いました。
――イベントひとつ取っても『トライ&エラー』でやってみて成功したら「やってみてよかった」という実感が得られる感じですね。あと甘味処巡りもよくされているようですが。
三橋さん パレットでは高校や大学のようなサークル活動を行っていて、そのなかの一つで洋菓子や和菓子の名店、銘菓を求めて歩くサークルなのですが「ヒト」って何か楽しみがないと自分から前向きな気持ちで行動を起こす気にはなれないと思うんです。
元々家にいた時間が長いような方がここに来るだけでも頑張っているのに、さらにどこか行って、しかも基本は自分の足で歩いていくというので何か明確的な目標とご褒美を加えたいなと。じゃあ洋菓子や和菓子ならみんな好きだよねということで。
あとここは政令指定都市であり障害者福祉にも力を注ぐ千葉市で事業展開している事業所になりますので、市が関わっているまちづくり、イベント関連に出来るだけ参加していきたいなと思っています。
また現在はサークル活動日という活動する日を設けているんですけど、今は職員が計画を立てているので、今後利用者さん達が主導で決められたらいいなと思っています。
でも今現在も家にこもっていた人が休みの日に自分で足を運んでお店の方に何曜日が休みか聞きに行ったり、売ってる物を見たりしてネットだけでは拾えない情報とか職員に与えてくれる方もいるので、
それだけでもこのサークルが健康になるための一翼を担っているのかなとか、外に出ようとする前向きな気持ちをこの利用者さんは持ったんだなと思って、これはこれで自分で考えたアイディアですが現状的にはいい方向に向かっているんだなって。
利用者さんたちで回る場所を決めたりとかもして、現地についても利用者さん主体で話し合って工夫してるので「すごい」と思って。
外出イベントを通じてコミュニケーション能力の訓練というか勉強になってるなと思ったんで、「いいな」と思って見てましたけど。
――こういう取り組みでSSTのプログラムに自然となってるのですね。
このクリスマスの飾りつけも利用者さん達で考えられたんですか?
三橋さん クリスマス会が12月25日にあるんですけど、翌日の後片付けも含めて企画から準備段階とどれかしらに参加していただき企画書や装飾として形に残してもらいました。
私自身がお金をかけてしまい市販されたものを買っているところを、利用者さん達はネットで検索してサンタを折り紙で作ったり、ポインセチアを手作りしたりたくさん飾りつけを持ってきてくれてるので助かりますね。

事業所内のクリスマスの飾りつけ
就労移行支援所は背中を押し伴走するところ
――お二人にとってここで働かれているということは利用者さんの今後の未来を担っているという責任感のあるお仕事だと思うのですが、いかがでしょうか?
宍倉さん 利用者さんの人生は利用者さん自身が決めるので、あくまで就労移行というのはサポートであってレールを引くものではないし、レールを引いて向かわせるってことではなくて本人がこっちの道へ行きたいというのを後ろで押す、サポートするというのが就労移行だと。
利用者さんがこういうものをやりたい、こういう仕事がやりたいというのを第一優先としてじゃあそのためにはどういう風にやっていこうかというサポートが出来ればなと自分では思っています。
三橋さん 自立に向けた一助ですよね。基本的にはご自身で決めたいただくと。パレットにはいろんなプログラムをご自身で決めていただくというスタイルなので、最初に来たばかりの体験の方だと読書をしてるとかアニメの閲覧をしてる方も中にはいらっしゃるのですけども。
朝起きてここに来ることからスタートしてる方にとってはまずパレットに来所されることが到着地点なので、次はここに来てからの過ごし方を考えていただく。そうして越えられる課題を一つひとつクリアしてもらうこと。ただ2年間しか与えられない限られた時間のという中で過ごしていくうちに、本人が今やっていることと就職に向けて方向性がちょっとずれてきているなというのが感じられた時には、「こうだと思うんだけど、どう思う?」って形でゆだねて本人に決めてもらっています。
「今○○ばかりやっているけど、こういうこともをやった方がいいんじゃないの?」とか、いくつか選択肢を与えてあくまでご自身で決めていただくことで、今までだったら踏ん張れなくてすぐに諦めたり辞めてしまったところでももうちょっと頑張ろうかなと思えるかなと。自分の人生は人から押し付けられるものでもないし、誰かに決められたことで後悔したくもない。自分の人生は人にゆだねたりせず自分で決めたいですよね。
就労移行の事業所が関わることで、利用される方々の自立に向けた一助とゴールに向けて伴走が出来ればいいなと思っています。

一般社団法人 飛翔 パレット稲毛海岸